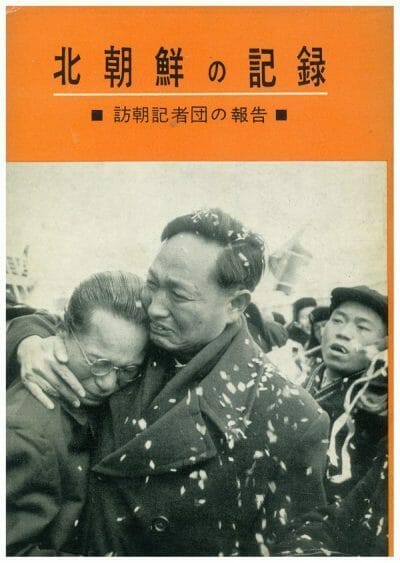本稿は、1960年に新読書社から発行された「北朝鮮の記録 : 訪朝記者団の報告 」を紹介しています。帰国事業当時「38度線の北」同様、大きな影響を与えたと思われる訪朝記事です。現段階でのコメントはつけません、一つの歴史的資料としてお読みください。
「帰国者」が平壌に着いた
産経新聞東京本社社会部 坂本郁夫

その日の平壌
その日、平壌の街は、快晴とはいえ、肌を刺すような北風が吹いていた。「今日の午後に、第一次帰国同胞が平壌に着きます。市民の間に、大変な歓迎熱がありますが、寒いので、婦人こどもは出迎えを辞退するよう、呼びかけています」私たちは、通訳氏から、こんな〝前触れ〟を聞きながら朝食をすませた。
一九五九年十二月二十日。
前日、空路平壌入りして、一夜明けたばかりの私たちである。商船のこと等、皆目わからないだけに、単なるニュース予告と聞き流して、夢中で真っ赤なキムチを頬ばっていた。
ところが、午前中のスケジュールである、祖国解放戦勝記念館見学に出かけようとして驚いた。まだ十時前だというのに、ホテル前の大通りには、色とりどりの造花を持った人たちが、あるいは無言で、あるいは歌を歌いながら、行列をつくって平壌駅の方へ歩いている。
「あの行列は何ですか?」
「帰国同胞歓迎の市民たちですヨ」
「まだ三時間もありますヨ」
「そうです。市民たちは、心から彼らの帰国を歓迎しているのです。家にじっとしていられないのです」
いつまでも続く行列をみて、私たちは「こりゃあ大変なことだ」と、つぶやいた。
記念館見学を終えて、そそくさと駆けつけた平壌駅前。そこで私たちは、思わず立ちすくんでしまった。
どこから、こんなに、沢山の人たちが出てきたのだろうか。駅前の広場も、駅から帰還者の宿泊所になる大同橋ホテルまでの幅六十五メートル、長さ一・六キロのスターリン通りの両側も、人また人。
手に手に、造花やノボリや小旗を持った人たちは、「キムイルソン・マンセイ」(金日成万歳)を叫んだり、「金日成将軍の歌」を歌ったりしている。駅前の広場は、大きな興奮で、どよめいているのだった。
聞いてみると、一五万人の平壌市民が、〝帰国同胞〟を迎えるため、自発的に出かけて来ているのだという。
朝鮮に来る前、私は、帰還第一船を送り出すために新潟に行かされていた。帰還列車が新潟の駅に着くたびに、駅前を埋めた朝鮮総連や帰還協力団体の人たちの、派手な歓迎風景、そして「マンセイ」の越えで送られて出ていった船……。
過去数年間にわたって、私は〝引き揚げ記者〟として、中国やソ連からの帰国邦人を興安丸や白山丸で迎えにいったこともあるし、舞鶴で、待ちわびる肉親たちと一緒に出迎えたこともあった。
日本人の帰国は、敗戦による抑留の果ての帰国であったため、歓迎風景といえば、肉親との再会に〝涙する〟場面ばかりだった。ところが、新潟で見た、こんどの帰還は、〝涙〟の見えない、〝歓声〟一本槍の場面ばかりだった。
その〝歓声〟うずまく帰還風景に、いささかドギモをぬかれ、圧倒された私たちが、わずか一週間のあとに、この平壌での、新潟の規模を数十倍上回る、〝歓迎風景〟をみたのである。
「ヤッテクレタ」
私は、思わず、こう唸って、立ちすくんでしまったのである。
北風と、大群衆の歌う「キムイルソン・チャング」(金日成将軍の歌)が舞う中に、帰還者を乗せた特別寝台列車が、平壌一番ホームに入ってきた。二十日午後一時五十三分。歌声と歓声がひときわ高まった。
清津から平壌までの二十四時間近い、汽車の旅にも疲れも見せない帰還者たちが、窓から手をふり、小旗を出して、これに応える。
駅ホームの中央に陣取った李一卿赤十字副社長、李周淵迎接委員会委員長た、政府高官の顔が、ほころびた。
「案内人」と朝鮮文字で書いた腕章の女学生たちが、長いホームをいったりきたりして、帰還者たちを誘導する。
一人、また一人、帰還者たちは、ホームを埋めた人垣きから、五色の紙吹雪の嵐をうけながら出口へと向かう。
「梯団長」と書いた赤いタスキをかけた老人が、若い男の肩車にのせられてやってくる。レイをかけ、帽子も服も、小さな顔も、いっぱいに細かい紙吹雪を付けたこどもが、手を引かれてやってくる。
拍手をして出迎える政府高官。
「よく帰ってきたネ」――そう言わんばかりに、差し出す高官の手を、しっかり握り、思わず「マンセイ」と叫ぶ老人。
手拍子がとられ、狂気のように旗がうちふられる。帰還者も、その歓迎のウズにまき込まれて、思わず歌を歌い、拍手をする。
やっとの思いで駅の外に出れば、今度は十五万人という、身動きの出来ないほどの人たちに囲まれる。バスに乗るが、バスは人にさえぎられ動けない。
薄い絹の服を着た若い男女が、朝鮮古来の民族芸術などの踊りや歌を、バスの前で帰還者にひろうするのである。
太鼓が鳴り、笛がふかれ、弦楽器が鳴る。それにあわせて、ピンクやブルーの絹の衣裳が舞う。駅前広場は、それこそ、アリの入り込む隙もないくらい、ギッシリつまっているのである。「歌」、「踊り」、「マンセイ」の交錯。
どのくらいたったのであろうか。その広く、大きな 〝環〟が少しずつ、バスの通る道を開けていった。僅か一・六キロ離れた大同橋ホテルに、バスの先頭が着いたのは、汽車が着いてから三時間もたったあとだった。
「まったく、何かに憑かれているような騒ぎだネ」
――昼飯を抜いたことも、ノドがかわいたことも忘れて、ただ、やみくもの歓迎風景に、モミクチャにされた私は、誰かに話しかけながらタイプをたたいた。
――帰国者の一人・盧敬子さん(二四)=川崎市浜町四の一=の話 昭和薬科大学を辞めて平壌薬科大学に入るために来ました。もちろん生まれたのは日本で、両親と妹は日本に残っています。やはり感激と喜びで一杯です。元気にこれからやって行こうと思います。
――日本人妻の山中鈴子さん(二六)=千葉市緑町=も「元気で着きました。これからのことは全部おまかせします。歓迎は涙が出るほど嬉しく、知らない国という不安は消え飛びました」と語った。
行数の関係もあるし、電報事情もあって見たり聞いたりしたことの全部を書くことは、もちろん出来ない相談だった。しかし、私たちは書くべきことは、みんな書いた。
ローマ字の電報は、平壌―上海―東京と打電され、二十一日付各紙の朝刊のトップを、賑やかに飾った。
「北朝鮮帰還者感激の平壌入り 市民十五万が出迎え 手に手にバラの造花持ち」
という見出しで………。
〝何かに憑かれたような騒ぎ〟という言葉を私は使った。
平壌の街中が、誰か、名指揮者のタクトで大交響楽団が、整然と、一大シンフォニーを奏でるように、秩序整然と「歓迎劇」を、〝上演〟しているからである。
日本だったら絶対に、こんな風景には、おめにかかれない。東京といわずに、どこか小さな県庁の所在地くらいの都会を想像したって、小さな村を考えたって、出来そうにないことである。
お国柄が違うといってしまえば、それまでだが……。
しかし、なぜ、この国の人たちは、こんなに、憑かれたような騒ぎを続けて、帰還者を迎えるのだろうか。――こんな疑問が湧いて来るのは当然だ。
田仁徹、林哲さんら、われわれを案内してくれた人たちは、この疑問に、こう答えてくれた。
「朝鮮が北朝鮮と南鮮(韓国)の二つにわかれてから十五年。北朝鮮はその間、国連軍を相手に戦った。一九五三年七月、朝鮮戦争が終わったときは、傷ついた国民と、全くの焼け野原だけが北半分に残されていた」
「それから六年余、北朝鮮は遅れをとりもどすのに必死だった。学生も、婦人も、労働者も、みんなが動員されて、祖国復旧に死力を尽くした。機械なんかはもちろんなかった。シャベルとモッコ、それだけだった」
「シャベルとモッコで焼け跡を掘りかえし、土を捨て、道をつくった。有り合わせの機械で、家を建てた。レンガ工場がないので、手でレンガを焼き、そのレンガを使ってレンガ工場を建て、住宅用のレンガをつくった。戦災で廃品同様になった工場の機械を復旧させて、どしどし立派な機械をつくるようになった」
「一千万国民の血と汗の結晶が、今、目の前にある平壌です。もちろん、まだ日本をはじめ、先進国に遅れを取っている。しかし、かつて、国もなく、貧乏のどん底にあえいでいた朝鮮から見れば大きな発展であり、喜びである」
「金日成首相同志(同志という言葉をよく使う)も言っているように、今の北朝鮮は、まだ〝中農〟ほど度の段階だ。しかし〝貧農〟からは足を洗った。貧しいながらも〝中農〟なのである。二年前だったら、恐らく、帰国同胞を受け入れることは出来なかったろう。帰国同胞を引きとるだけの〝実力〟というか、〝下地〟が出来あがったのである」
――国を持った喜び。復興の喜び――その具体的な現実として行われた「帰還」。それだからこそ、国民の一人一人が、帰還者を歓迎し、国中が「帰国」一色に塗りつぶされたのである。憑かれたような騒ぎが持ちあがったのである。
両親と離れ、はじめてみる故国に、期待と不安を抱きながら、第一次帰還船に乗ってきた盧敬子さんとは、平壌駅前に並んだ帰国者輸送バスの中で逢った。
バスの中で、東京のデパートの包み紙に包んだ荷ものを持ち、何かしょんぼりと、立っていた帽子を被った若い女性。
「お疲れになりました?」
「ええ船酔いしまして………..」
歯切れの良い日本語が、彼女の口から、とび出した。私の日本語を聞いてか、元気をとり戻したようだった。
父親が朝鮮総連の幹部であること、母も妹も川崎に残っていること。どうしても〝祖国〟に帰りたかったこと。薬剤師になることを志していること…..などが、スラスラと語られた。
――清津に着いた日、零下十五度に下がった寒暖計をみると、思わず、両親や妹のところに、飛んで帰りたい気持ちになりました。たった一人で、見も、知りもしないところにきたんですもの。
――だけど、船から一歩上陸した途端、私の、そんなセンチメンタルな気持ちは、どこかへとんでいってしまいました。出迎えの人たちが五万人もいたでしょうか。雪の降る、冷たい戸外で、私たちを待っていてくれ、それこそ、抱きかかえるように、休憩所に連れていってくれました。
――あったかい紅茶と、ビスケット。外の寒さとは比べものにならないくらいのスチームのきいた部屋。朝鮮服を着た若い女の人たちが、手をとるようにして、何でもしてくれる。温かい紅茶を、大事に、ひと口、ひと口すすって、私は、新しい〝祖国〟に住む覚悟をかためました。
――大の男が、〝俺たちには,こんなに歓迎される理由がない〟〝ほんとの親子だって、これほど温かく迎えてくれない〟といって泣き出し、奥さん方は奥さん方で、〝もったいないもったいない〟と涙を流していました。
――清津に四日間いて、十九日の午後三時半、私たちは汽車に乗りました。この間中、私たちはゴチソウぜめにあいました。毎日、食べ切れないほどの料理が出ました。日本にいる朝鮮人の生活というのは、一部の人を除いては、皆、いちように苦しいものです。食べたいと思っても、買えなかった肉や魚。それが毎食、もてあますほどつくのです。
――「こどもが、リンゴを食べたいといっても、日本では買ってやれなかった。ほんとにリンゴの夢を見たことも有ります。それが、帰還船にのってから、毎食つくのです。こどもが、喜んで、リンゴを食べている姿をみて私は涙が出て、しょうがありませんでした」といった奥さんもありました。
――清津から平壌まで、二十四時間近い汽車の旅でしたが、汽車がとまれば、駅毎に盛大な歓迎をうけ、湯茶の接待もうけました。ほんとに、どういったら良いか、わからないくらいの感激です。
――食べなれない辛いものも食べて、胃をこわしたら…というのでしょう。清津の食べものは、私たちに向くように辛みをへらしてくれていたということです。
――何だか、ジーンとなっちゃった。
敬子さんは、バスのシートの背に顔を伏せてしまった。
清津に向かう
翌二十一日、私たちは、第一次帰還者の盧敬子さんら九百七十五人の来た道を辿って平壌を発って清津へ向かった。
敬子さんたちが、口を揃えていう〝大歓迎〟を、この目でたしかめたかったからである。
十六時間五十分の汽車の旅を終えて、降り立った清津には雪が舞っていた。
早速、清津市迎接委員会をたずね、金弘善委員長、金洛濬委員らと逢った。
金委員長らの話によると、帰還が決まってから、わずか四十日間で、五階建て百七十四室、千人を収容出来る、アパート形式の〝仮泊所〟(招待所)をつくったという。
「朝鮮人の生活はオンドルとは切り離せません。だから、このアパートも、全部オンドルです」という。
招待所には、食堂、病院はもちろん、図書室、娯楽室、銀行、日用品売店などがある。
招待所には、百五十人の専任職員がいるが、このほか、帰還船が着く埠頭にはアルバイト学生の〝案内人〟が数百人いる。船が着く日は、学校は休み。職場は保安員だけを残して、市民の大半が出迎えに行く。
人口二十万の清津の、四分の一、五万人が第一船を出迎えたという。
「第一船を迎えて、受入れ側である、あなたたちは帰還者を、どう見るか」
――私たち記者団は金委員長に、こんな質問をした。
「抱き合って泣いた人もあるし、二十年ぶりにくらいで逢った肉親の変わりように、驚いて声も出なかった人もある。〝劇的〟というほかはないだろう。帰ってきた人は、殆んど泣いた」
「印象に残ったことといえば、三十年振りに、オンドルのある部屋に入った老人が、涙を流しながら、骨まであったまるような気がする。ほんとに、固かった骨もとける…と何度もくりかえしたこと。日本で生まれたこどもたちが、祖国の土を、はじめて踏んで、祖国の水をのんだ、その姿――この二つは、私の記憶から永久に消えないだろう」
二十三日は、また、雪だった。零下十二度までさがった寒暖計は、いっこうに、あがろうとしなかった。
メリヤスのズボン下二枚に、毛のズボン下、長袖のシャツ三枚にワイシャツ、セーター、背広、オーバー、帽子は北京で買った耳かくし付き。自動車のシートに座れば、ちょっとやそっとでは立ちあがれないくらい、ダブダブに着込んだ私は、港へいった。
真白な粉雪が、サラサラと音をたてて降り、〝最高の寒さ〟に、唇も紫色になる。
だが、その寒さの中で、頬を真っ赤に染めた人たちが、じっと船の到着するのを待っていた。おとなも、こどもも……。
中には、薄いチマ・チョコリ (朝鮮服) を着た朝鮮民族芸術サークルの男女もいる。真っ白な制服の看護婦もいる。
思わず通訳の朴さんに
「あれで寒くないんですかネ」
「いやァ、皆んな慣れていますョ」という答え。思わず首をかしげてしまった。
「八・一五記念日とか、メーデーとか、国の、お祝いの日には、国が号令をかけなくても、市民たちは、自発的に町に集まり、お祝いをします。こんどだって、船がいつに着くとわかれば、みんなが、自発的に出て来て、こうして出迎えるのです。国には命令はありません」
「学校だけは休んでいますが……。みてごらんなさい。みんな楽しそうに、歌を歌い、踊りを踊っているではありませんか。心から帰国同胞を待っているのです」
――その〝自発的〟な歓迎風景は――船が着くまでは、埠頭の休憩所の前で、船が岸壁に着けば船の前で、帰還者が埠頭から六・二キロ離れた招待所に入る時は、招待所の前へ…と移動してゆく。
招待所に、帰還者が全員入ってしまえば、こんどは、その前でプカプカ、ドンドンと、「キムイルソン・チャング」の大合唱。
雪を真白にかぶりながら、手袋もしない小さな赤い手に、時々、息をプゥーとふきかけながら、小太鼓をたたいていた、小学校一年生の女の子の姿が印象的だった。
二十三日は、第二次帰還者が清津に着いた日。船の到着が午後一時三十五分だったが、清津の町や埠頭で、歓迎の騒ぎが繰り広げられたのは、午前九時から午後、夜も暗くなるまで。
抱きあった。泣きふした。ぼう然とした。われを忘れて「マンセイ」「マンセイ」と大声で叫んだ――船到着から招待所までの光景は、この言葉で表現するだけでよいだろう。
――精力的な歓迎。
平壌ー清津と見て歩いて感じたことである。朝鮮の人は、あの辛い唐辛子とにんにくが大好きだ。私たちが東京で食べる朝鮮料理なんて、本場のとくらべたら〝朝鮮料理〟ではないような気がする。
その唐辛子とにんにくが、精力的な、力にあふれた身体をつくる。この国民が、サッカーをもっとも愛好することでも、その〝力〟が分かる。
その〝力〟が、国を持った喜びと復興の喜びの具体的なあらわれとしての〝帰還〟で、最高度に出される。
雪も、寒さも吹き飛ばす〝熱い歓迎〟。
ほんとに、〝熱い歓迎〟だけがあるのである。
北朝鮮政府は、在日朝鮮人の帰還問題が、日本政府で検討されはじめ、藤山外相が、「近く帰還を実現させる」と、はじめて明らかにした一九五九年一月、早くも、その受入れ態勢をつくりはじめていた。
「貧乏のどん底にあり、食を求めて海外に散っていった人たちを、今、国の基礎が固まり、充分とはいえないまでも、国民のみんなが安楽に暮らせるようになった時に、 喜んで迎え入れ、われわれと同じように安楽な生活を享受させること。これは、同胞愛からほとばしる民族的義務ではないだろうか」
これが、その理念であった。
このため、政府には李周淵副首相を委員長とする帰国同胞迎接委員会が出来、帰還者受け入れの一切を行うことになった。
もちろん、この下部組織として、日本の県に当たる道をはじめ、市、郡にも、それぞれの迎接委員会が出来、受入れ対策が、各道、市、郡別に、それぞれきそわれた。
「いつでも帰ってらっしゃい」――一九五八年一年間で、平壌だけで二万三千世帯分の住宅が建った。このスピードでいつでも帰還者用の住宅が出来る。何人でも、直ぐに受け入れられる態勢がつくられていたのである。
金日成首相も、この帰還者受入れには、大変な気の使いようで、帰還者には、当座の生活安定のために、一人あたり二百円(日本円三万円相当)の補助金を出すことを指示した。
二百円といえば、北朝鮮では、労働者の給料の四ヶ月分くらいに当る大金。迎接委員会では、現金を与えるよりも、必要な日用品をとり揃えてやった方が、とにかく便利であるという見解をとり、現金は一人当たり二十円(日本円三千円)を補助金として出し、残りの金で、家具、日用品を買うことにした。
この国は、社会主義国である。自由主義国の日本などとは、恐らく、すべてが違う。第一、失業がない。国民の一人、一人が、もし、その人が働ける環境にあれば、必ず〝職〟がある。
だから、帰還者も、例外なく、その能力、技術、知識を一〇〇パーセント発揮でき、生活が、急速に安定できるように、配置される。
住宅があって、日用品も揃い、職場もきまる。あとは、こどもの教育。
教育については、これも、政府の方針で、日本で大学の学生だったものは、無試験で、該当学年の大学に編入される。
いまの、北朝鮮の学校制度では、大学に入るには、高級中学を卒業後、一度、社会に出て、二年くらい、みっちり働き、〝技術〟を身につけてからでないと、大学は入学資格がないが、帰還学生には、これが適用されない。ひとつの組織で動く、この国にあっては、まさに破格の出来事だ。
中学生(高級、初級とも)、小学生については、語学の関係もあって、日本の学生より、一年さげて編入される。つまり、日本で高三だったものは、朝鮮の高級中学二年に編入される。
もちろん、独身大学生用に、大学の寄宿舎は、空けてある。手ぬかりはない。
帰還者が、新潟で船に乗れば、あとは、ベルト・コンベア式に、スムースに、ことがはこび、新潟出発後、十ー十五日くらいで、北朝鮮に、安住の地が出来る仕組みだ。
張さんの話
張姞洛さんは、夫の崔元喜さんとともに、一家七人で、第一次帰還船で帰って来た。夫の崔さんは、茨城県古河市で、朝鮮総連茨城西南支部長をつとめていた人。
「日本にいたときは、とても惨めでした。お祭りの夜に、娘に一枚の着物も買ってやれず、一銭のこづかいも持たせなかったことは、いまでも悲しい思い出です。夫も、いつも熱心に仕事し、上の人ともよくやっていましたが、その勤め先がつぶれたりすると、こんどは、次の仕事に不安が来る。戦争中はある工場の課長までつとめましたが、戦後は、苦しくなる一方。ついに、組織の仕事をするほかはなくなりました。大きくなったこどもの就職のことも考え、帰ることにしたのです」
張さんは、帰還の事情を、こう話した。
その張さん一家だが、二十日、平壌の大同橋ホテルに、ひとまず、落ちついてから、わずか四日間で、夫の崔さんの仕事をはじめ、こどもたちの学校も、全部きまった。
政府の迎接委員会の人が、本人の希望を聞き、政府の計画とにらみ合わせて、仕事をきめてくれるのである。
崔さんは、日本にいた時、苦学して日大法学部を卒業した経歴があるので、委員会の人は、
「裁判所に勤めたらどうだろうか」といったそうだ。
崔さんは、
「とんでもない。私には、堅苦しいところはむきません」と答えたという。
結局、崔さんは、簿記を習ったことがあるというので、平壌精密機械工場の経理をやることになった。
長男正竜君(二一)は、日本にいたとき、芝浦工大土木科三年に在学、東都大学野球リーグ戦では、四番を打って、一塁をまもって、ちょっと有名だった。〝永山正竜君〟。正竜君は、金策工業大学に編入された。
長女英子さん(一八)は音楽大学へ、次男栄司君(一五)は、高級中学、次女成子ちゃん(一一)は、初級中学、三男正守君(九つ)は、小学校にあたる人民学校へ。
住宅は、平壌市外城区橋口洞十四号アパート七十四班。三間で浴室付きのアパートが与えられた。引っ越しは二十五日。新潟を発ったのが十四日だから、十一日目に、新居におちついたことになる。
大同橋ホテルから、アパートに来て、ほんとに驚くことばかりです――張さんは、こう語る。
「家に入ってみたら、テーブルやタンスはもちろん、七人分の椅子、茶碗、湯のみ、手拭いが全部、キチンと置いてあるではありませんか」
「そして、台所には、一ヵ月分のお米と、肉、魚、野菜、調味料が置いてあり、お豆腐やキムチまである。ちょっと、みて下さい。あのお豆腐、まだ残っているんですョ。食べ切れなくて…」
「引っ越したら、直ぐ、隣組組織の〝女性同盟〟の人が来てくれて、荷物をほどくのや、掃除を、いろいろ手伝ってくれました。ここはオンドル式に出来ているでしょ。お米の炊き方や、オンドルの火のつけ方を、どうしようかと思っていたんです。そんな心配なんか、どっかへいってしまいました」
「慣れるまでオンドルをたいてあげましょう――といって、女性同盟の人が、毎日、あさに来てくれるのです。見よう、見真似で、私も、大分、うまくなりました。同盟の人たちは、それこそ、喜んでくれました」
「ええ、もう大丈夫です。夫は十五の時、朝鮮を離れ、日本に行きましたし、私も、こどものころに日本に移りました。だから、来る前は、やはり、ちょっと不安はありました。しかし、それも、もう解消しました。これからは、一家七人、生まれ変わったつもりでやっていきます。
「日本の、私たちの知っていた人たちは、みな親切でした。ただ、朝鮮人ということで、常に仕事(就職)に対する不安がありました。こどもを野球選手にしたのも、就職ということを考え、不良学生にならないで、明るく生きてゆけるようにと考えたうえでのことでした。でも、いまとなってみれば、そんな心配もいりません……」
黒いチマ・チョゴリを着た張さんは、十二月二十七日、新居を訪れた私に、こう明るく話してくれたのである。
張さん一家とともに第一次船で帰った九百七十五人の人たちは、どのように配置されたか。委員会に聞いてみた。
独身学生所帯を除く二百四十二世帯の内、百六十七世帯は工場に、五世帯が農村に配置された。工場に配置された者の中には、普通工員でない技師、技術者や、事務を執る管理部門系統も含まれる。
残り七十世帯は、社会団体、文化団体などに配置された。写真技術者は写真報道社、芸術係者は芸術団体へ。医者は保険機関へ。その他、国家機関といわれるお役所や、職業同盟、女性同盟など、社会団体へ…。
もちろん学生は希望通り、学校へ入れられ、大学生二十四人のほとんどは、金日成大学に編入された。
平壌におちついたのは九十六世帯。残りは平安南道、平安北道に配置された。
委員会の話では、日本で個人企業をしていた人は、その人の能力や希望によって工場などに配置、部、課長、技師になって働いてもらう。第一船の人たちの中には、自分の仕事を選ぶことが出来ない人がいたが、この人たちには、まず各地を見学旅行させ、そのうえで、仕事を選んでもらうようにしたという。
国家の計画と、個人の希望――その二つによって、帰還者は、北朝鮮到着後十~十五日で、各地に散ってゆく。
ある日本人妻
本川玉代さん(三三)は、東京都世田谷区上馬二の四六から日本橋の商事会社に勤める夫、玉末守さん(三七)とともに、第二次船で帰った〝日本人妻〟だ。
おからばかり一ヵ月も食べたこともあるし、メリケン粉だけの日が二た月も続いたことがある。日本ではそれほど苦しかった。
川越にいる七十二才の老母は、
「あんたは、夫を好きになって結婚した。国籍が違っても、好きな人と結婚するのは当たり前。どんなに苦しくても、夫と別れたりしてはダメだ。立派な国際結婚なのだ」と、常に玉代さんを激励していたという。
〝朝鮮に行ける日が来る〟――新聞が伝えたのは、一九五九年の一月だった。
玉代さんは、是が非でも、北朝鮮に行こうと、夫に話した。夫の玉さんは、
「折角、立派な勤め先があるのに。もう少し経って、様子をみてから……」と消極的だった。
朝鮮人である夫が消極的で、日本人である妻が積極的に「帰還」をしたいと願った。
はたからみれば妙な、とりあわせだった。しかし、玉代さんは、その日から、一生懸命朝鮮語の勉強にはげんだ。
週二時間ずつ二回の勉強――その熱意に動かされたのか、夫の玉さんも一緒に帰るといい出した。
「字は読めるんですが、話が通じないので…」
玉代さんは、私に逢ったとき、こう漏らしていたが、いまでは、もう立派に会話も出来るようになっただろう。
玉代さんの話ではないが、帰還が実現するまでには、かなりの曲折があった。
六十万人を越える在日朝鮮人のうち、一九五九年一月現在、北朝鮮に帰還を希望するものは十一万七千人(朝鮮総連調べ)に達していた。
これより先、一九五八年九月八日、金日成北朝鮮首相は、在日朝鮮人の要望にこたえ、「在日同胞の帰国を歓迎する。新しい生活ができるように、すべての条件を保証する」と演説、九月一六日には、南日外相が、帰還船希望者引き渡しに関する日本政府宛の声明を発表。一0月一六日には、金一副首相が、旅費負担と配船の準備があるという談話を明らかにした。
日本国内でも、このような動きを反映して、「在日朝鮮人帰国協力会」が発足、朝鮮総連とともに、帰還実現に積極的に動き出した。
政府は、このような背景の中に、北朝鮮帰還問題を検討した結果、日韓会談が、いつになっても再開されそうもないこと。帰還希望者を、いつまでもとめておくことは、居住地、帰還先選択の自由に反すること――などの理由から、人道問題として早急に措置するという方針を決め、二月十三日、閣議了解で、「帰還」を決定した。
そして、韓国への影響もあるため。厳正中立な立場にある赤十字国際委員会に、その仲介をとってもらうことにし、直ちに日赤本社を通じて、その要請を行った。
人道を旗印とする赤十字にバトンが渡ってから、日赤は、島津社長を中心に、全社を挙げて、帰還問題ととり組んだ。
四月十三日から、スイスのジュネーブで開かれた日朝赤十字会談は、ある意味では難航した。
北朝鮮側が、まず、赤十字国際委の介入は不必要であると、日本案に反対したからである。
日本側としては、韓国からの横ヤリを防ぐため、公正な第三者である国際委の「介入」を必要条件とした。つまり、国際委が、その帰還が本人の自由意志であるか、どうかをたしかめないことには、韓国に対し、納得のゆく説明が出来ないからであった。
四月十三日から六月二十四日まで、会談を重ねること十八回、やっと、日朝両赤十字の間で合意が成立した。そして、協定が出来あがり、国際委の承認をまって、調印することに話し合いがついた。
日本側は葛西副社長、北朝鮮側は李一卿副社長を団長とする両代表団は、お互いに、よく、話し合った。
もちろん、「人道」と「政治」は、紙一重でその間のかね合いも、むずかしかった。島津社長が、ともすれば、〝政治的〟に動こうとする政府に、ダメ押しの陳情をするため、岸首相や藤山外相に「直訴」したこともあった。
妥結した朝、記者団とともに徹夜し、日赤食堂でつくった味噌汁をすすりながら、島津社長がいった言葉――
「やっと肩の荷がおりた感じだョ。戦争中は交換船でフィリピンの米軍捕虜たちに援護物資を配り、戦後は国際委の代表と一緒に国内の捕虜収容所を回って捕虜送還をした。昭和二十八年には一月に中国、十月にソ連にいって邦人引揚げ協定をつくった。どれも割合にうまく、ことが運び、今度ほどのことはなかった。こんどが一番大変だった」
――ほんとに実感がこもっていて、忘れることが出来ない。
私は、この交渉の間、はじめから終わりまで、ずっと日赤を見て来た。日赤がどんなことを考え、どのようにつとめて来たか、恐らくほとんど全部を知っている。
だから、この島津さんの言葉が、忘れられないのかも知れない。日赤は、とことんまで、全力を出して、帰還実現に努力した。
私は、北朝鮮を去る、案内役の前夜、田さんをつかまえて、大いに、この点を強調した。
誤解があってはならないからだ。
田さんも、ジュネーブに、労働新聞特派員として出かけた、ベテラン記者。
「日赤と、北朝鮮赤十字の、言わば民間外交が結実したのです。現に、帰還者が続々帰って来ているのではありませんか。人道万歳です」
田さんは、こう言っていた。
日朝赤十字で話し合いが着いたものの、今度は国際委がいっこうに腰をあげなかった。自由主義陣営から、社会主義国への帰国という点もあったろうし、韓国、米国とのかね合いもあったろう。
しかし結局は、国際委も、「人道」の名において、乗り出しを決定し、八月一三日、インドのカルカッタで、日朝両代表による調印が行われた。
やがて、国際委代表が来日し、九月三日は、帰還の手引きともいう「帰還案内」が、日赤から発表された。そして九月二一日から、一斉に受付開始を予定した。
ところが、帰還者世話人の立場にある朝鮮総連では、「帰還案内」のうち、「意思確認」「面会、外出禁止」など三項目は、人権無視であるとして反対、申請拒否という闘争に出て、混乱した。
実際のところ、日赤自体、この三点については、初めから、これほど強くしようとは考えておらず、むしろ国際委の助言によって〝完璧なもの〟が出きたことに、苦慮さえしていた。
一時は、帰国タナあげ論も出たが、政府、日赤、朝連と、あっせんの役を買って出た衆院外務委員会委員を中心とする国会議員団との間で話し合いが着き、十月二十八日、ようやく解決した。
十一月四日、機関申請は再開された。開店休業を続けていた窓口は、四五日振りに活気を呈した。初日だけで三千八百六十三人が、申請した。
この日をどんなに待ち望んでいたことだろう。どの窓口も、喜びにあふれた帰還希望者でいっぱいだった。――
ふりかえれば長い、長い間でした――本川玉代さんは、平壌の大同ホテルで、こう、つぶやいた。
「いつかは、夫の国に来ると思っていたのですが……」
その玉代さんは、大みそかの夜、金日成首相招待の新年迎えの宴会に招かれた。
その日、玉代さんはホテルの流し場でこどもの靴下を洗っていた。
「奥さん、ちょっと集まって下さい」
誰かが、呼びに来たので、行ってみると、ホテルにいる第二次帰還者の内、十三人が大みそかの金日成首相招待宴に呼ばれたというのである。
日本人としては、玉代さんが、たった一人の代表だ。
「一九六〇年を迎える新年宴会に
同志を招待する
一九五九年十二月三十一日二十三時
内閣庁舎
内閣」
玉代さんは、朝鮮文字で書かれたインビテーション・カードを握ってはなさなかった。
その夜、玉代さんは、まだ落ち付き先が決まらないので、荷ものをほどくことも出来ず、新潟以来、ずっと着ているピンクの手あみのセーターに茶色のスラックス姿で宴会に出かけた。
豪華なシャンデリアに輝く一室で、政府、党幹部とともに、金首相招宴にのぞんだ彼女――。
金首相がつかつかと、そばに来て、
「乾ぱいしましょう」と言った。
隣りにいた議員さんが通訳してくれた。
玉代さんは、ブドウ酒をグッとのみほした。甘いも、辛いも分からなかった。ただ、心臓がドキドキして、顔がほてっただけだという。
「まったく、夢みたいだ。死ぬまで、このインンビテーションカードは離しません。だが、このブドウ酒とともに、いままでの苦労も、みな、吹きとんでしまいました。あとは、私の身体の半分に流れている日本人の血に、はずかしくないよう、朝鮮の人に笑われないように頑張ります」
私は玉代さんの幸福を祈って別れた。
――帰還者の一人、一人が、私の逢った限りでは、みんなしあわせそうだった。
北朝鮮帰還を実現に移したことは、これら帰国した人にとって、よかったことだ。
帰還実現に努力した日赤の島津社長らに、是非一度、この光景をみせてあげたい。
島津さんは、きっと、帰還者の一人、一人と、手をとりあい、抱きあって、ともに喜ぶことだろう。
人道の花が、みごとに実った――
この玉代さんに逢った日、私は、こんな原稿を,夢中でタイプしていた。
ある運転手君との会話
東京に帰って、二、三日たった、ある日、乗っていたタクシーの運転手君に話しかけられた。たまたま私と同僚が話していた、朝鮮の話を、「悪いとは思いながら聞いたんですが……」という前置きで、彼は、こういった。
「私は朝鮮人です。三月に向こうに帰ろうと思っているものです。北朝鮮に新聞記者の人たちが行って、いろいろ報道してくれたおかげで、よく事情がわかりました。しかし、一つだけ得心のいかないことがあります。良い点だけが強調されて、悪い点がほとんど書かれていないのです。日本の人から見れば、まだまだ遅れている点が多いでしょう。そんな点を、私たちは知り、そして帰りたいのです。行ってから、がっかりするよりも、ここはこういう国だということを、あらかじめ頭に入れておきたいのです」
私自身は、この点も新聞に書いたつもりだった。だが、この運転手君の質問に、あらためて答えなくてはならなかった。朝鮮総連の都内のある区の委員をしているという彼は、喜んで、私の話を聞いてくれた。
日本人の目から見たら、北朝鮮は、未だ、たしかに日本の水準には至っていない。
金日成首相が、われわれ記者団と逢ったとき、「朝鮮は、やっと〝中農〟程度になったばかりだ。これから、みんなで建設して、そして富んでからゼイタクをする」と言った。
国内のどこを見ても、「建設」一本ヤリである。〝千里馬運動〟という生産運動が展開され、一九六〇年は、緩衝期という調整の年、すべてを一九六一年からの第二次五ヵ年計画にかけている。
第二次五ヵ年計画を終えれば……。それまでは国民の消費生活は、最低線の保証にとどめられている、未来に希望があろうというものだ。
現在は――
衣、食、住、は基本的に保証されている。「基本的」というのは、最低線保証のことだ。
一般労働者の平均給与五十円。そのうち家賃は水道、電気料込みで一円、米代十五日分一円二十銭(三人家族)。副食費三十~三十五円という支出である。学校、病院は無論タダ。社会主義国だけに福祉面は発達している。しかし、われわれ日本人から見たら、このような生活内容では、息苦しさが残る。いわゆる〝消費面〟が全くないからだ。
ガソリンをソ連からの輸入にあおぐ北朝鮮では、ガソリンは血の一滴だ。お役所の自動車も所有台数の半分以上(たとえば教育文化省では八台中五台は動いていない)が動いてないし、タクシーなどはもちろんない。ライターも見かけない。東京の自動車洪水など、この国では、〝お話〟としてしか聞かれないだろう
自動車は月産三千台、リヤカーも量産されていない。お隣の中国では、いまや自転車ブーム。ある大臣は「自転車は、近く月産三万台に増やす。運搬機関が発達しなくては、なんとも仕様がない」とわれわれに言った。
平壌市内の帰還者落付き先を回っていた時、あるアパートの前に、新品の電気冷蔵庫と電気洗濯機が、荷造りしたまま置いてあった。
北海道の釧路からきたという夫婦は、われわれの好い取材対象になった。
――これは両方とも新品ですね。
「ええ、住んでいた家を売って、買って来ました」
――これから荷をほどくのですか。
「まア。この冷蔵庫と洗濯機は当分しまっておきます。なぜかといえば、このアパートで、これを持っているのは私たちだけなのです。招待所の人は、どんどん使っていいと言ってましたし、電気関係のお役所に頼めば、コンセントをつけてくれたり、、電気をくれるといってましたが、みんなが苦労して復興に努力しているのに、自分たちだけが、これを使う気持ちには、とてもなれません。アパートの人が、みんな持つようになったら、出して使います」
通訳の田さん、朴さんが口をはさんだ。
「あなた、なぜ使わないんです。使っていいんです。招待所でも、そう言ったでしょう。我が国は、社会主義国です。しかし個人の所有物にまで干渉はしません。個人が個人からサクシュすること――女中を置いたりすることは禁じますが、個人の所有物には何の制限も加えません。車を持って来た人にはガソリンを配給してあげるし、電気製品を持って来た人には電気をあげましょう。使っていいんです」
しかし、材料の関係から蛍光灯、ラジオの国産がむずかしく、電気洗濯機、冷蔵庫も、まだ試作の段階という。この国の事情を、恐らく知っている、この帰還者の夫婦は、果たして、電気製品を使えるだろうか。
「せっかくそう言うんだから、使おうや」と考えるのは、われわれ日本人。
通訳氏の説明は、たしかに理くつにあっているが、絶対主義の社会主義国で、そんなワガママが許されるかどうか。
われわれ記者団の中でも、この電気製品をめぐって、「使える」「使えない」の論争がまき起こったが、私は後者に手をあげる。
北朝鮮滞在中、幾度となく見た、あの、組織的な大衆動員による〝大歓迎風景〟。その〝組織〟の中に、新しい一員として入った帰還者は、やがて、もっとも早い機会に、みんなの力で同化され、第二次五ヵ年計画の貫徹のために働く、千里馬運動の一員になってしまう――大歓迎風景をみていて、私はこう感じた。
「アパートの人たちの洗濯を一手に引きうけたら……….」ーー記者団は、こんな言葉を残して夫婦のもとを去った。
苦労して過ごした日本での生活の末、やっと手に入れた新品の電気製品が、物置から出されて、陽の目をみる日の、早く来ることを祈りながら………。
「北朝鮮に行けば、職がある。日本にいるより、ずっと楽になる」
こんな気持ちで来られたのでは困る。新しい北朝鮮に住むには、それだけの覚悟はいる。車が縦横に走り、電気製品が普及し、ダンスホール、キャバレー、バーと夜の歓楽街のある日本とは、自らちがう。遊ぶ施設、ゼイタク品はない。ただ〝建設〟あるのみの社会。
末来を楽しみに生きる国――それが北朝鮮という国だ。
こどもだってそうだ。アメリカのスポーツである野球はない。こどもを連れてくる人は、日本のマンガ本や、おもちゃは、船に乗る前に、こどもから離し、こどもを、一日も早く、北朝鮮になれさせるために、北朝鮮の本を見せ、北朝鮮の遊びを覚えさせなければならない。親として、こどもには、ぜひ、こうやってやりたい。
――ある主婦は、しみじみといっていた。
朝鮮人の運転手君は、こんな、私の話を、だまって聞いていた。
「よく分かりました。みんなが知りたがっていることなので、早速、この話しをしてやりましょう」
「私だって、今、毎月四万円から五万円の収入があります。一応、家具も揃っているし、それほど苦しい生活はしていません。向こうに帰れば、今より苦しく、厳しい生活をしなければならなくなるでしょう。それでも私は帰るつもりです」
「私が、帰ることに、ふんぎりをつけたのは、こどもが可哀相だからです。日本にいて大学を出ても、朝鮮人なので、良いところでは雇ってくれません。せっかく育てても、こんな惨めな目にあわせてしまう。親として、しのびないのです。出来るなら、生まれ、育った〝日本〟を、いつまでも、〝第二の故郷〟として、美しい思い出の中に残し、いつか、日本に〝里帰り〟する日があるように、こどもたちが悲哀にぶつからない前に、帰りたいのです」
ある高名な評論家は、ラジオの座談会が終ったあと、私たちに、こう言ったことがある。
「戦争中なら、一億総決起とか何とかいって、国民を一線に揃えさせることが出来るが、平和な時に、千里馬運動などのかけ声で、国民を動員出来るなんて、大した国だ。私はそこに頭を下げる。だけど、その国に住みたいかと聞かれたら、ノーという。いってみたいかと言われたら、イエスと答える」
日本人の社会主義国北朝鮮に対する、代表的な観方だろう。
生活環境から来る、一つの息苦しさ、圧迫感――自由に育ったわれわれには、到底たえられないものがある。
「しかし、帰った人たちが、みな、未来に希望が湧き、苦しさが未来の繁栄につながる建設の一課程として消化されてゆくのなら、いいではないか。日本人と朝鮮人との間にはものの考え方に、色々違う面があるだろう。帰った人たちが、喜んでくれさえすれば、私たちのやった仕事が、赤十字の精神にのっとった人道主義としての輝かしい業績になるだろう」
と、島津日赤社長はいう。
帰る人も、受け入れ側も、双方が喜びの中に続けられる帰還。
日本海エキスプレス(急行)という愛称をうけた二隻の帰還船は、人道の使途として、きょうも日本海の荒浪を蹴たてて、ピストン輸送をいっている。
日本海エキスプレスの平安な航海を祈ろう。
北朝鮮帰還が実現するまでの経緯
▽一九五八年九月八日=金日成首相、「在日同胞の帰国を歓迎する」と演説。
▽同九月十六日=南日外相、帰国希望者を引き渡してほしいと日本政府宛の声明を発表。
▽同十月十六日=金一副首相、配船準備ある旨を語る。
▽同十一月十七日=東京に「在日朝鮮人帰国協力会」誕生
▽一九五八年一月二十九日=藤山外相、参院本会議で「在日朝鮮人の北朝鮮帰還は近く計画を発表出来る」と声明。
▽同二月二日=岸首相、衆院予算委員会で「送還を行う」と発言。
▽同二月十三日=人道問題として赤十字国際委員会介入のもの、帰還を行う旨の閣議了解が行われた。また、この日、国際委も自由意志による帰還なら援助すると公表。
▽同四月十三日=日朝赤十字第一回会談ジュネーブで開催。北朝鮮はソ連船を使用、諸手続は朝鮮総連を窓口にして行いたいと主張。
▽同四月十五日=第二回会談、北朝鮮側、帰還者希望者の意思確認を拒否。
▽同四月十七日=第三回会談。北朝鮮側、国際委介入に反対、日赤は朝鮮総連名簿尊重を拒否した。
▽同四月二十日=第四回会談。意思確認などにつき、日赤側、文書で説明。
▽同四月二十二日=第五回会談。意思確認問題で合意成立。
▽同四月二十四日=第六回会談。北朝鮮側、限られた範囲での国際委介入に同意、北朝鮮側の帰還計画案を提示す。
▽同四月二十九日=第九回会談。日赤「実務に国際委介入」「朝連名簿は認めない」など十七項目を回答。
▽同五月二日=第九回会談。日赤、「苦情処理委員会」設置を含んだ協定草案を提出。
▽同五月四日=第十回会談。北朝鮮側「苦情処理」は混乱をまねくと反対。
▽同五月六日=第十一回会談。日赤、さらに整理した協定草案を提出、朝連名簿不採用、北朝鮮代表の入国を拒否。
▽同五月二十日=第十三回会談。日赤、最終案を提示。
▽同五月二十五日=第十四回会談。「苦情処理」「国際委介入」で、日本側最終案を拒否すると北朝鮮側が主張。
▽同五月二十六日=両首席会談。北朝鮮側、日本案を変えねば決裂、二十九日までに回答せよと主張物別れ。
▽同五月二十八日=北朝鮮側、国際委介入の用語「指導」を「観察」にしてほしいと非公式に申し入れる。
▽同六月一日=第十五回会談。―日本側、最終案を提示。
▽同六月四日=第十六回会談。北朝鮮側、日本修正案に不満示す。
▽同六月九日=政府、日赤は北朝鮮側の主張を容れ、苦情処理で新提案を準備。
▽同六月十日=第十七回会談。日本側「苦情処理」を撤回、事実上妥結す。
▽同六月二十四日=第十八回会談。在日朝鮮人の帰還に関する協定(付属書を含む)及び共同コミュニケの草案完成。国際委の承認を待って調印することにきまる。
▽同六月二十九日=国際委、「帰還問題は再検討の要がある」と言明。
▽同七月六日=国際委、介入決定は。さらに時間がかかるとして承認を延期。
▽同七月七、九日=北朝鮮、日本両赤十字代表団一旦帰国。
▽同七月二十一日=ハーター米国務長官、ボアシエ国際委員長と会談、米側の意向を伝えたと言われる。
▽同七月二十四日=日赤、国際委の承認をうけ、北朝鮮赤十字あて、カルカッタで協定調印を行いたいむね打電。
▽同八月十三日=カルカッタで日朝両赤十字代表の手により帰還協定に調印さる。
▽同八月二十三日=赤十字国際委マルセル・ジュノー副委員長、「介入」のため来日。
▽同九月三日=日赤、ジュノー氏の助言により「帰還案内」を発表。
▽同九月二十一日=帰還申請受付開始。朝鮮総連、「案内」に不満として、申請拒否闘争を展開、各窓口混乱す。
▽同十月十日=北朝鮮赤十字、帰還案内は協定違反だと日赤に抗議。
▽同十月十三日=日赤、第一船は十一月十一日新潟に入港するよう要請。
▽同十月十九日=北朝鮮側、業務はかどり次第配船すると日赤に返電を打つ。
▽同十月二十日=日赤、十一月十二日第一船新潟出航を断念。新潟日赤センター開所。
▽同十月二十二日=衆院外務委員会岩本伸行、帆足計、穂積七郎代議士ら、日赤、朝連の間のあっせんにのり出す。
▽同十月二十七日=政府、「帰還案内」を「実務細則」で緩和することに決定。
▽同十月二十八日=朝鮮総連、あっせんを了解。反対闘争とりやめを決定。
▽同十月二十九日=米国務省、帰還問題で日本を全面支持する。韓国の自重を望むと、初めて公式見解を発表。
▽同十月三十一日=日赤、国際委の了解を得て、帰還案内の緩和を指示。
▽同十一月四日=全国三千六百五十五カ所の日赤窓口で申請を再開。
▽同十一月十六日=帰国祝賀大会に民団、右翼千人が押しかけ、混乱、七人が逮捕される。(東京池袋)
▽同十二月十四日=第一船、新潟を出港。年内三回配船。